2025.02.21
お知らせ製造業において、外観検査の自動化を検討している担当者も多いのではないでしょうか。外観検査を自動化すれば、人手不足を解消しより効率的に業務を進められます。
この記事では外観検査の自動化について、メリットや導入方法を解説します。自動化を導入する際の課題も解説するので、ぜひ内容を確認してみてください。
外観検査の自動化とは?

外観検査の自動化とは製造業において、完成した製品や部品の外観検査を機械を導入して自動化することです。人の力で外観検査を行っている事業者が自動化を行えば、今ある人手を外観検査以外の業務に回せます。
外観検査を自動化すれば、不良品の流出を防ぐとともに不良品ができる原因を見つけて改善につなげることが可能です。そのためには、外観検査で見つかった不良の種類を分析して、検証する必要があります。
外観検査を自動化する際は、製品の外観を撮影するカメラとそれを分析するシステムを導入します。あらかじめ用意された見本画像と異なる部分があるかをチェックするシステムが主流でしたが、近年はAIを搭載したシステムでより正確に画像判定を行えます。
外観検査を自動化するメリット

外観検査を自動化するメリットには、以下があります。
- 人手不足を解消して検査品質を保てる
- 検査時間を短縮できる
- 検査にかかるコストを削減できる
それぞれについて詳しく見ていきましょう。
検査品質を保てる
外観検査を自動化することで、検査品質を保つことができます。人間が作業をおこなう場合と比較するとエラーが起こりにくいだけでなく、全数検査で記録を残せることで履歴を確認することが可能です。
人手が足りていない状態での外観検査は、担当者に過剰労働をさせる可能性も否定できません。過剰労働で疲れている状態で目視の外観検査を行えば、担当者の集中力も下がり検査品質が下がってしまいます。機械は疲れることがない分、均一な品質の検査が可能です。
また、AI検査では規定に適合しているかどうかを全数検査をおこなうことができます。AIを用いた全数検査では、接続したセンサーから製品や部品の状態に関するデータを収集することができ、品質を見分けるためのアルゴリズムを構築。正確な検査ができるのにくわえ、トレーサビリティで過去の履歴をさかのぼることもできます。
検査時間を短縮できる
検査時間を短縮できることも、外観検査を自動化するメリットの1つです。検査時間がどのくらい短縮できるかは製品の種類などで異なるため一概に言えませんが、90パーセント検査時間が短縮できる場合もあります。
また、機械を用いた外観検査は24時間稼働できます。検査時間の短縮と24時間稼働で、人手では難しかった全数検査も可能です。
検査にかかるコストを削減できる
外観検査を自動化するメリットには、検査にかかるコストを削減できることも挙げられます。外観検査の自動化は、設備投資で膨大な費用がかかると思われがちですが、長い目で見ると自動化した場合の方がコストを削減できることが多いです。
外観検査の導入には、数百万以上かかります。これに加えランニングコストが初期投資の5~10パーセントかかります。一方、人手で検査した場合は採用費用や給与、社会保険料などで一人当たり月額数十万円かかるので、外観検査を自動化した方がコストを削減できると言われています。
外観検査の自動化を導入する方法

外観検査の自動化は、以下の方法で導入します。
- 現状の課題を定義する
- 自動化する内容を決める
- 自社に適したシステムや機材を選ぶ
- 試験利用する
- 導入をはじめる
それぞれについて詳細を確認していきましょう。
①現状の課題を定義する
外観検査を自動化する際は、まず現状の課題を定義しましょう。課題が分かっていないとどのようなシステムを導入すればよいのか判断できず、自動化の効果が思っていたより得られない場合もあります。
課題を定義する際には、以下の項目を検討しましょう。
- 生産数と検査能力の現状
- 現状の検査員の必要数
- 期待する品質と検査員の能力の差
- 検査員による精度のばらつき
- 検査記録の電子化ができているか
- 不良品の原因分析ができているか
上記の課題を定義することで自社の検査に足りていない部分を明確にでき、導入するシステムを選びやすくなります。
②自動化する内容を決める
課題を定義したら、自動化する内容を決めましょう。内容を決めずに全部自動化しようとすると、膨大な費用がかかってしまいます。欠陥品をシステムで選別し、キズなどの最終チェックを人間が行うなど、どの範囲を自動化するのか検討しましょう。
どのような検査を自動化したいのかを明確にすることは、適切なシステム選びにも繋がります。外観検査はシステムによって得意な検査が異なるので、「高速な検査」や「微小な欠陥の検査」など、自動化に求める点を明確にしましょう。
③自社に適したシステムや機材を選ぶ
自動化する内容が決まれば、自社に適したシステムや機材を選んでいきます。たとえば、外観を撮影する際に使うレンズは、ピントの合う距離が機材によって異なります。そのため、検査の対象となる製品のサイズに合わせて選ぶようにしましょう。
システムについても、AIを搭載しているか、どの程度の分析が可能なAIなのかなどの違いがあります。自社が課題としている点や自動化する内容として決めた項目をカバーできるシステムを選びましょう。
④試験利用する
使うシステムが決まれば、自社用にシステムの構築やチューニングをして試験利用します。試験利用で、求める内容の検査ができているのか、システムや機材は適切に稼働するのかを確認できます。
外観検査の自動化を導入する際には、一般的にここまでの過程で数ヶ月から半年かかります。希望する導入時期から逆算して準備をはじめましょう。
⑤導入をはじめる
試験利用が問題なければ、いよいよ自動化システムを導入します。試験利用では確認できなかった不具合が生じる可能性もあるので、導入後は検査精度をチェックして必要があればチューニングするようにしましょう。
導入後も、検査精度を落とさずシステムを長く使えるように適切なメンテナンスを行いましょう。また、自社製品の品質をより向上させるためにも、外観検査システムと検査結果を分析し続けることが大切です。
外観検査を自動化する際の課題

外観検査を自動化する際には、以下の課題があります。
- 導入や維持にコストがかかる
- 自社製品に合うようカスタマイズする必要がある
- ティーチングマンの確保が難しい
それぞれについて詳しく解説していきます。
導入や維持にコストがかかる
外観検査の自動化は、導入や維持にコストがかかります。一般的に外観検査の導入には、システムや機材代として数百万以上かかり、維持費用もその5〜10パーセントかかります。大きな初期費用がかかってしまうので、まとまった資金の準備が必要です。
外観検査の自動化を導入する際には、助成金を利用すれば初期費用を抑えられます。たとえば、「ものづくり助成金」は、中小企業・小規模事業者を対象として費用の一部を助成してくれる制度です。助成金制度は自治体によって異なる場合もあるので、導入を検討する段階で調べてみましょう。
自社製品に合うようカスタマイズする必要がある
外観検査の自動化を目的として検査機器を購入した場合は、自社製品に合うようにカスタマイズする必要があります。一般的に検査機器は汎用性を重視して製造されますが、検査する製品は導入先の企業によって異なるため、調整が必要です。
より自社製品にカスタマイズされたシステムを使いたい場合は、オーダーメイド装置の導入も検討しましょう。オーダーメイドの分費用がかかるので、既存製品のカスタマイズと比較検討することをおすすめします。
ティーチングマンの確保が難しい
外観検査を自動化する際の課題には、ティーチングマンの確保が難しいことも挙げられます。ティーチングマンとは、機器の導入や検査の動作をシステムに記憶させる業務を行う従業員のことです。外観検査の導入にはティーチングマンが必要ですが、自動化が急速に進んでいるため人材確保が難しくなっています。
ティーチングマンを確保する方法には、自社の従業員をティーチングマンに育成する方法と外部から招き入れる方法があります。ティーチングマンの育成は数年かかるので、自社の従業員を育成する際は計画的に行いましょう。
マシンビジョンを導入するなら、ICS SAKABEに相談
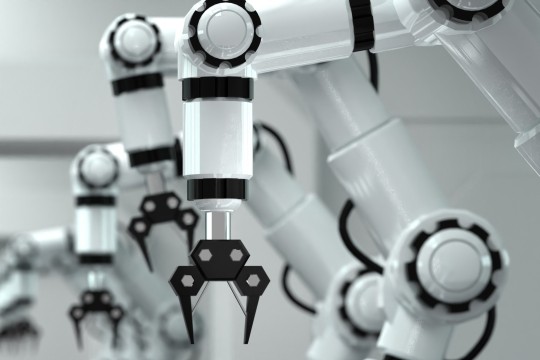
人手が足りていない場合や検査精度を向上させたい場合は、自動化の導入が特におすすめです。人に代わって製品チェックを行う「マシンビジョン」で、自動化を導入し事業を持続できるものにしましょう。
ICS SAKABEでは、マシンビジョンの導入を検討されている企業様のサポートを行っています。導入前の課題のヒアリングからメンテナンスまで一括でおこなっており、機械の使用に慣れるまでは従業員に対して教育も実施。ワンストップでマシンビジョンの導入をおこなっているので、コストを抑えたい企業にもおすすめです。外観検査の自動化を検討している企業様は、現状の課題を相談するだけでも問題ないので、ぜひお気軽にお問い合わせください。
まとめ

この記事では、外観検査の自動化についてメリットや導入方法を解説しました。外観検査を自動化することで、今の業務をさらに効率化し検査精度を上げることが可能です。
外観検査のメリットは、以下の3つです。
- 人手不足を解消して検査品質を保てる
- 検査時間を短縮できる
- 検査にかかるコストを削減できる
外観検査の自動化を導入する際には、半年以上の期間がかかる場合がほとんどです。事前に導入時期を検討して、計画的に自動化を進めましょう。
